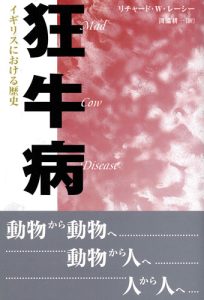「図書新聞」1994 年 4 月 4 日付より転載
「昭和天皇の戦争責任を鋭く問う」という広告文が「時節柄まずい。右翼を刺激する。広告企画の趣旨に合わない」などの理由で、出版広告の掲載を拒否された緑風出版が、昭和天皇の死亡直後の 1989 年1月 18 日、中日新聞社を相手取って契約不履行による損害賠償を求めていた事件で、東京高等裁判所(小川英明裁判長)は、一審判決を変更、同社に賠償を命じる逆転判決を去る(94 年)2月 28 日、言い渡した。
小社は、中日新聞社が発行する東京新聞1月18 日付別刷「『昭和史』特集保存版」へ「ドキュメント昭和天皇」(田中伸尚著、全八巻)、の広告出稿を同社広告局から直接勧誘を受け、これに応じた。ところが、ゲラ校正が済んだ後になって、昭和天皇の死亡直後の異様な〝追悼・自粛〟ムードに畏怖した同社が、「右翼のウォッチャーがしっかりみているから困る」など冒頭の理由を言い立てて、突然、広告掲載を拒否してきたため、小社が東京地裁に訴えていた。この時、同様の理由で同紙に拒否された出版社が、他に二社あった。
91 年 11 月 26 日の第一審判決は、広告契約の成立自体を認めず、小社の請求が棄却されたため、これを不服として控訴していた。高裁判決は、「遅くとも広告文が最終的に決定された」時点、つまり小社のゲラの責任校了の時点で契約が成立したと認定した上で「控訴人(緑風出版)と被控訴人(中日新聞社)との間で控訴人が主張するとおり広告掲載契約が成立したものというべきであり、被控訴人は、同月 18 日発行の『昭和史』特集保存版に『ドキュメント昭和天皇』の広告を掲載しなかったものであるから、控訴人に対し債務不履行の責任を免れないものというべきである」と判示し、一審判決を全面的に否定した。
また、「被控訴人は、本件広告の掲載を拒絶した理由として、本件企画の趣旨は昭和天皇の追悼をすることであり、本件広告文は右趣旨に合わなかったからであると主張する。しかし、仮に被控訴人において本件企画をそのように予定していたとしても、本件企画書には、そのような趣旨の記載はなく、他に本件契約成立前に被控訴人から控訴人に対しその趣旨を伝えたことを認めるに足りる証拠はなく、かえって証人西田の証言及び控訴人代表者尋問の結果によれば、西田を含む被控訴人の社員等も控訴人代表者に対し、最後に(中略)本件広告を掲載できない旨を連絡する際に、本件企画が右趣旨のものであることを告げるまでそのことを一切言っていないことが認められるのであって、本件広告の掲載契約が成立した後になってその掲載を拒絶することを正当化しうるものではなく、被控訴人は、これによって債務不履行の責任を免れ得るものではない」と断じ、小社の主張を認めた。その上で一審判決を変更し、中日新聞社に1万 500 円の支払いを命じた。
請求額は大幅に減額されたものの、1円でもとれれば勝ちという裁判で、小社の主張が全面的に認められた逆転勝訴であった。
裁判は債務不履行による損害賠償請求事件という形をとりながら、実は「昭和天皇の戦争責任を鋭く問う」という広告文を理由に、出版広告の掲載を拒否できるのかという言論、表現の自由の問題が問われていた。それは同時に、日本出版学会会長で、ピンクチラシ裁判の弁護人でもあった清水英夫氏が「出版の自由は印刷、広告から流通まで確保されて初めて成り立つ」(「朝日新聞」1989 年2月 26 日付読書欄)と語るように、出版の自由と天皇制とのせめぎあいでもあった。そして、読者の立場に立ってみれば、広告を通じて出版物を知るという知る権利が侵されたという問題でもある。「『東京新聞』のこの別刷特集は、国民統合の象徴である昭和天皇の崩御に際して発行される日本有数の日刊紙の特集であるという性質上、一般社会通念上からも、社会慣行上からも、国民の総意を踏まえ、天皇追悼の趣旨を根底とする企画であったことは明らかである」(被控訴人準備書面第五)などという主張を、中日新聞社は繰り返した。
この裁判は、日本の新聞マスコミが天皇制に対してどのようなスタンスをとっているかを、改めて白日の下に晒した、内外二千数百万人の死に直接に責任のある昭和天皇の戦争責任を問えないジャーナリズムが、はたしてジャーナリズムの名に値するのであろうか?
(「図書新聞」1994 年 4 月 4 日付より転載)
*附記/完敗した中日新聞社は結局、上告を断念、緑風出版の勝訴が確定した。
-
 ドキュメント・昭和天皇─第八巻 象徴¥ 3,600 (税別)
ドキュメント・昭和天皇─第八巻 象徴¥ 3,600 (税別) -
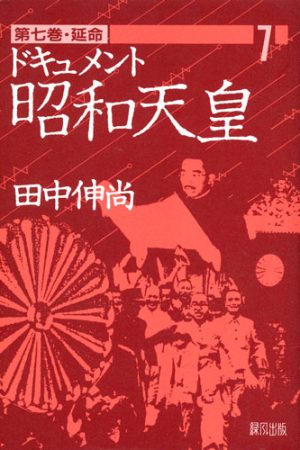 ドキュメント・昭和天皇─第七巻 延命¥ 2,500 (税別)
ドキュメント・昭和天皇─第七巻 延命¥ 2,500 (税別) -
 ドキュメント・昭和天皇─第六巻 占領¥ 2,000 (税別)
ドキュメント・昭和天皇─第六巻 占領¥ 2,000 (税別) -
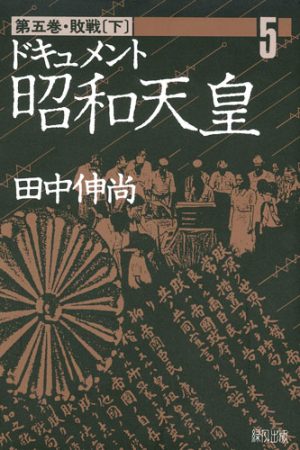 ドキュメント・昭和天皇─第五巻 敗戦〔下〕¥ 3,200 (税別)
ドキュメント・昭和天皇─第五巻 敗戦〔下〕¥ 3,200 (税別) -
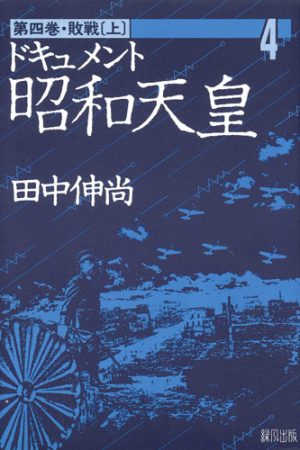 ドキュメント・昭和天皇─第四巻 敗戦〔上〕¥ 2,800 (税別)
ドキュメント・昭和天皇─第四巻 敗戦〔上〕¥ 2,800 (税別) -
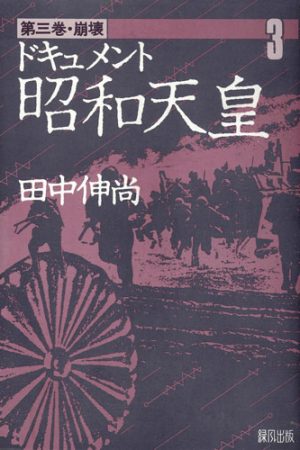 ドキュメント・昭和天皇─第三巻 崩壊¥ 2,400 (税別)
ドキュメント・昭和天皇─第三巻 崩壊¥ 2,400 (税別) -
 ドキュメント・昭和天皇─第二巻 開戦¥ 2,200 (税別)
ドキュメント・昭和天皇─第二巻 開戦¥ 2,200 (税別) -
 ドキュメント・昭和天皇─第一巻 侵略¥ 1,900 (税別)
ドキュメント・昭和天皇─第一巻 侵略¥ 1,900 (税別)