書籍内容
山口研一郎[著]
四六判上製/248頁/2500円+税
ISBN978-4-8461-2501-1 C0047
高次脳機能障害は、病気やけがによって脳に損傷を負うことで、主に精神上の変異や視覚障害、聴覚障害など、日常生活や社会生活に支障が生じる状態である。
本書は著者が約25年間、高次脳機能障害に関する臨床経験の中で、病態を通じて相談に応じてきた当事者・家族、また「日本高次脳機能障害友の会」を始めとする全国の会関係の方々、第三者的援助者、専門職の声を一つにまとめたものである。
そして、高次脳機能障害の原因や誘因が職場環境など社会的要因からきていること、個々の自助努力では既に限界にきていることから社会的支援が必要であることなど、「高次脳機能障害支援法」制定に向けて何が盛り込まれるべきなのかを提言した。(2025.2)
■内容構成
はじめに・3
第一章
発症の原因・誘因からみた高次脳機能障害への
社会的支援の必要性
17
1 交通事故や仕事中の事故....................................................................................
19
(1)頭の損傷・19
(2)脳内の血流や酸素の途絶・21
2 仕事上の過労・ストレス.................................................................................... 25
(1)脳卒中(脳血管障害)・25
(2)心筋梗塞・心停止・27
(3)ウィルス性脳炎・30
3 自然災害..............................................................................................................
31
(1)地震による家屋の倒壊・34
(2)救助活動の際の被災・36
4 脳の予防的手術...................................................................................................
38
5 他人からの暴力行為...........................................................................................
42
第二章
高次脳機能障害を取り巻く社会
47
1 生産性を重視し競い合う社会............................................................................
48
(1)効率化社会の元凶とは・48
(2)「社会的共通資本」にまで拡がる効率化・53
(3)医療・福祉の変質の実態・57
(4)競争、合理化、ノルマ化、生産性重視の渦中に置かれる高次脳機能障害・64
2 人と人との関係の希薄化─孤立度が高まり「無縁社会」へ.......................
69
(1)人々の関係の変遷を辿る(私が見てきた風景)・6
9
(2)人間関係の希薄化、地域共同体(コミュニティ)の崩壊の現実・77
(3)高次脳機能障害の人が感じる究極の寂しさ・82
3 ITやAI(人工知能)の導入.............................................................................
86
(1)ITやAIの導入の実態・86
(2)哲学者マルクス・ガブリエル氏の警告・88
(3)「科学主義」に関する私たちの体験・94
4 解決の糸口とは...................................................................................................
10 0
第三章
高次脳機能障害当事者の置かれた特殊な心理的状況
105
1 「社会的被害者」としての自分から抜け出せない............................................
10 6
2 二次的反応として生じる心理学上の変化.........................................................
110
3 「社会に受け入れてもらえない」「役割を与えてもらえない」.........................
112
4 益々強まる孤立感から絶望の極地へ.................................................................
113
5 年齢や立場によって異なる苦悩........................................................................
115
6 泥沼から抜け出す方策とは................................................................................
118
第四章
高次脳機能障害当事者・家族が望んでいること
123
1 怪我や病気の初期・リハビリ期(発症後六カ月以内)............................................
124
(1)医師・看護師・療法士による病態説明・124
(2)臨床心理士、医療ソーシャルワーカーよりのアドバイス・126
(3)福祉行政より社会サービス利用についての説明・129
2 慢性期(発症後六カ月以降).....................................................................................
130
(1)医療機関の役割・131
①長期にわたる診察・評価・診断の必要性・131
②認知リハビリの実施(グループ療法の効用)・133
③当事者・家族への周知・135
④福祉関係書類の作成・142
⑤自賠責保険・労災保険上の後遺障害認定(発症後一年半経過以降)・145
(2)就労のための準備・150
①「障害者総合支援法」の役割・150 ②就労移行支援事業所と就労継続支援事業所(A型・B型)・152
③就労を実現するための条件とは・153
(3)社会参加のための就労・155
①「障害者雇用促進法」に基づく障害者の就労・155 ②「合理的配慮」とは・156
③ハローワークと障害者職業センター・159
④雇用状況の実態・161
(4)地域生活・163
第五章
「高次脳機能障害支援法」に盛り込まれるべき内容 167
1 神経多様性疾患への理解.................................................................................... 167
(1)理解の一助としての法制化・167
(2)無限の可能性を有する存在として・172
2 社会的周知のために...........................................................................................
180
(1)マスメディアを通じた一般へのキャンペーン・180
(2)医師・看護師・福祉職への教育・182
3 具体的支援...........................................................................................................
187
(1)行政的支援・187
(2)医療の役割・188
① 生活の自立が厳しい場合・188
② 生活の自立が可能な場合・190
(3)福祉現場・192
(4)就労支援・194
(5)小児期・学童期の支援・195
(6)ケアラー(介護者)問題・201
(7)「親亡き後」・207
4 高次脳機能障害研究・治療・リハビリセンターの設立..................................
210
(1)「広大な宇宙」としての脳に生じた障害・210
(2)軽度外傷性脳損傷(MTBI)の解明・217
(3)認知症との関連・222
(4)予算的裏付け・230
おわりに・2
35
引用文献・参考文献一覧・
239

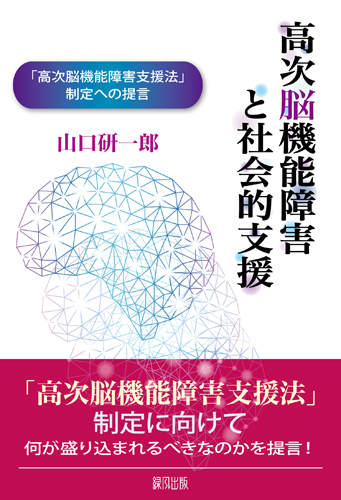
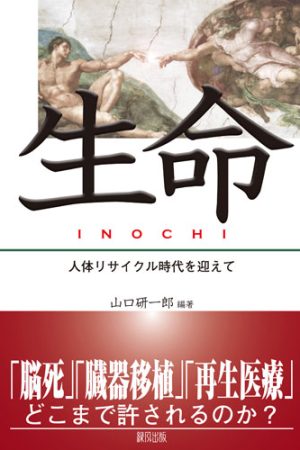
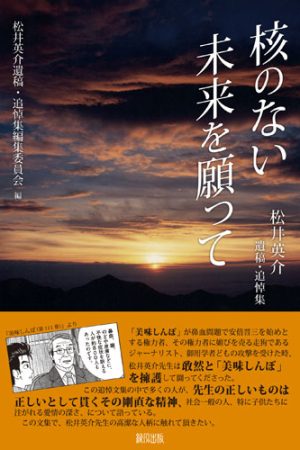
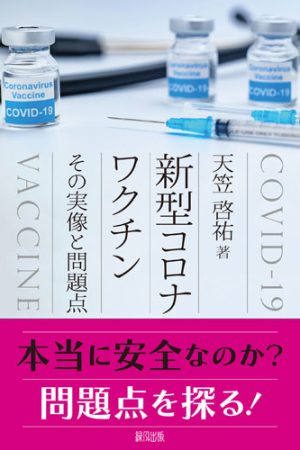
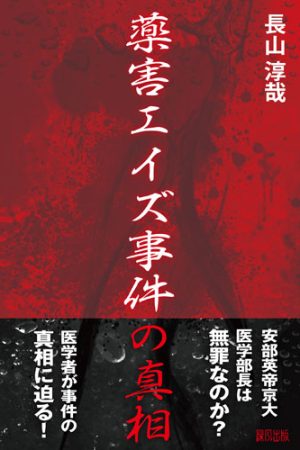
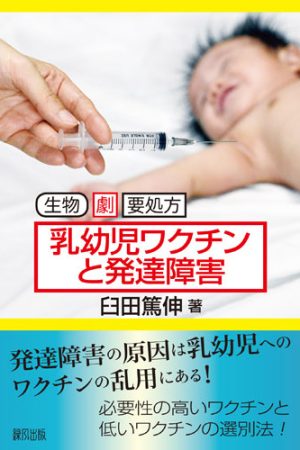
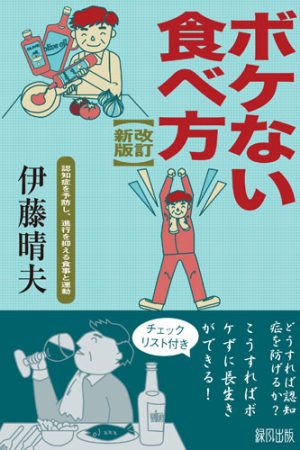
レビュー
レビューはまだありません。